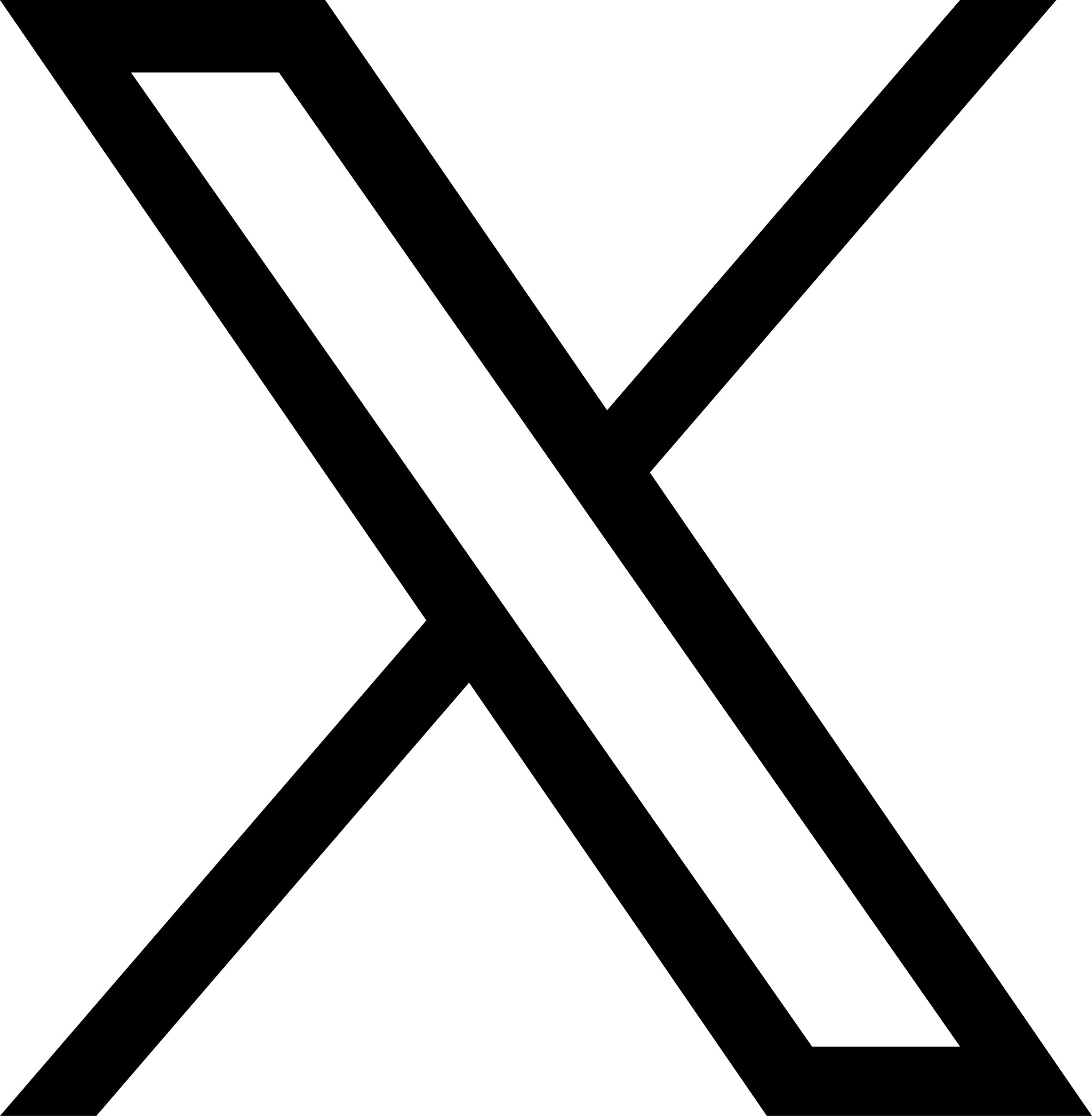「ERIKO YAMAGUCHI」途上国の街並みから生まれたコレクション 山口絵理子さんの挑戦とビジョン:前編
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」をミッションに、バッグやジュエリーなどファッションアイテムを展開するマザーハウス(MOTHERHOUSE)。代表兼チーフデザイナーを務める山口絵理子さんは、2022年に始動したアパレルブランド「ERIKO YAMAGUCHI」から2023 Autumn / Winter コレクションを発表するなど、新たなクリエーションを生み続けている。
自身の名を冠したブランドを展開するに至った背景と、今期のテーマになったインドとの関わり、さらにライフステージの変化を経た現在の心境について、前後編でお届けする。
見ただけで終わらせない。行動に移してこそ
 山口絵理子さん
山口絵理子さん――「ERIKO YAMAGUCHI」が生まれたきっかけを教えてください。
インド綿について考え始めていたある時、スタッフが小さな新聞記事に書かれていた「カディ」(インドで生産されている手紡ぎ・手織りの布)の展示会を教えてくれたんです。
その展示会に行っただけで終わっていたらERIKO YAMAGUCHIは誕生していないのですが、展示会で出会ったインド人の方が説明していることが本当なのかなと思って、すぐにアポを取り「現地で会おうね」って言ったのが良かったと思います。2週間後に約束どおりコルカタに出向いたら「本当に来たの?」と驚かれました(笑)。
見ただけで終わらせないとか、そういったアクションを起こすのは、自分の人生で本当に大事にしています。彼はそんな私の熱量に驚き、「展示会で色々な日本人に会ったけど、本当に来たのは君だけだから」と、村のいろんな場所に連れて行ってくれて。
そうしたら展示会で話していた通りで、本当に手仕事でこんな繊細なことをしているんだと感動して。その生地で「伝統的なインドの民族衣装ではない形の服をつくってみたい」と思ったのが始まりです。
――それはすぐに形になったのでしょうか?
コロナ禍においては、やりたいことのために時間を使わないともったいないと感じていたこともあり、まずは販売のことなど何も決めずに、自分が着たいと思う服をカディ生地でつくり始めて、気付いたらそれが16着にまでなって。これが最初のラインアップになります。
そして、社内の限られたスタッフにその服を見せた3週間後に、たまたま東急プラザ銀座への出店の話が上がってきたんです。それで「その場所に置いてみる?」となって。そんなことだったから、計画性はまるでなくて。
これまでどおり、店名は「MOTHERHOUSE」にしようと話していた時期もありましたが、自分の“好き”からつくったものだから、自分の名前で出すのがいいんじゃないかと、おそるおそるブランド名となる店名を自分の名前にすることを決めたんです。
事業計画のために何かを引き算してモノづくりをするのではなく、パッションからつくったものに後から名前が付くというプロセス、それはとても自然だし、あるべき姿かなと、覚悟を決めました。
――プレッシャーや不安があるなか、なぜそのチャレンジを選んだのですか?
東急プラザ銀座への出店は、最初、1年契約のお話で、自分の名前が付いたお店がもし1年で終わると思ったらそれだけで胸が痛くなるし、自分に恥ずかしくないものをつくるって一番ハードルが高い気がして、モノづくりのプレッシャーに耐えられるのか、不安は強くありました。
でももう40歳になったし、人生一度きりだしと思ったり。子どもを産んだというのもすごく大きかったかもしれない。大変さと動き出す喜びのどちらが上回るかよく考えたとき、つくる時のワクワクした気持ちが勝ったのです。
ファッションと研究の共通点とは? データサイエンティスト宮田裕章さんが語る
ともさかりえさんが手がけるブランド<MY WEAKNESS>が初のポップアップストアを開催