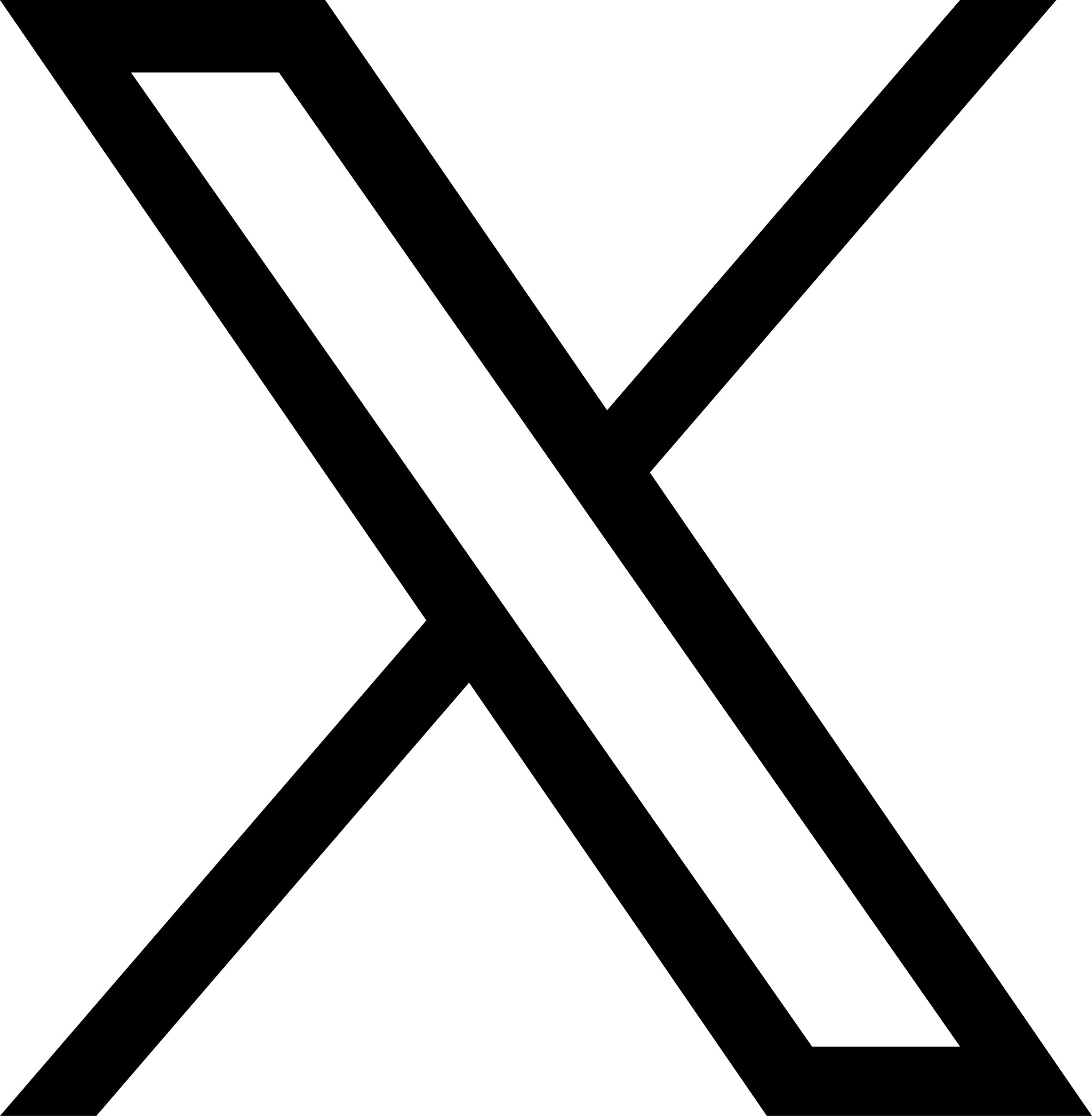【what to do】ブレッソンによる『湖のランスロ』、あるいは『たぶん悪魔が』。新宿で映画の臨界に立ち会う
㊧『湖のランスロ』© 1974 Gaumont / Laser Production / France 3 Cinema (France) / Gerico Sound (Italie)、『たぶん悪魔が』© 1977 GAUMONT
知的好奇心あふれる『マリ・クレール』フォロワーのためのインヴィテーション。それが”what to do”。映画好きなら、ぜひ駆けつけてほしい作品の上映が東京・新宿の映画館で始まった。『湖のランスロ』と『たぶん悪魔が』。いずれもロベール・ブレッソンが1970年代に監督した作品だが、全く古びない。オーバーアクションや説明過剰なシーン、そして効果音が頻出する現代作品にうんざりしている人にこそ、観てもらいたい傑作だ。日本では劇場初公開。映画表現の臨界に立ち会えるスリリングな機会でもある。
ブレッソン(1901-99)はフランスの映画監督。『罪の天使たち』(43)で長編デビューし、『抵抗』(56)、『スリ』(59)、そして『ラルジャン』(83)の監督として知られる。「モデル」と呼ばれる素人を俳優に起用し、禁欲的な倫理に貫かれた「シネマトグラフ」を追究。「撮影された演劇」とする「シネマ」とは一線を画し、ヌーヴェル・ヴァーグの作家らに計り知れない影響を与えた。
配給元にブレッソンのポートレートがないとのことで、筆者所有のブレッソン関連の本から、その姿を偲んでもらうことに……(撮影・高橋直彦) 彼の著作『シネマトグラフ覚書――映画監督のノート』(筑摩書房、87年)を翻訳した松浦寿輝さんは、その創作姿勢を「マサッチョのように孤高でありフェルメールのように潔癖でありセザンヌのように厳密である」とし、「ドビュッシーのように孤高、ハイドンのように潔癖、バッハのように厳密」とも言い換えている。ブレッソンの作品を観続けてきた人なら、それがあながち誇張とは言えないことに納得するはずだ。
もっとも、テレビドラマの作劇に慣れ、ヴィジュアル・エフェクトを駆使したハリウッドの大作に親しんできた人にとって、ブレッソンの作品は一見取っつきにくいかもしれない。モデルの表情は生硬で、台詞回しも一本調子。動作もぎこちなく、素っ気ないからだ。しかも、何を見せるかより、何を見せないかを重視したシーンが基本的に90分前後続く。ところが、その表現を眼と耳を駆使して注意深く受け入れていると、何とも艶めかしく、奥ゆかしいシネマトグラフが立ち上がってくる。そうなれば、ブレッソンの作品からもう目を離すことができなくなる。
アーサー王伝説に登場する王妃グニエーヴルと円卓の騎士ランスロ(左)の不義の恋を中心に、騎士道精神が崩壊していく様を現代的視点で描いた 今回、公開されている『湖のランスロ』(74)と『たぶん悪魔が』(77)もそう。前者が中世を舞台にしたコスチュームプレイ、後者は現代の環境問題や社会不安に言及した終末論的な作品と一応言うことができるかもしれない。しかし、作品を観れば、そうした分類などに何の意味もないことがすぐわかる。ヴィスコンティの『ベニスに死す』(71)などの撮影監督も務めたパスクァリーノ・デ・サンティスによる強度のある映像が4Kデジタル・リマスターで甦り、細心の注意を払って録取された音響と相乗しながら、私たちを映画表現の臨界に誘ってくれる。これらが40年以上前の作品だとは!
何を見せるかではなく、何を見せないかをブレッソンは大切にした 『湖のランスロ』が第27回カンヌ国際映画祭国際批評家連盟賞、『たぶん悪魔が』が第27回ベルリン国際映画祭銀熊賞(審査員特別賞)を受賞しているが、そうした周辺情報も作品を目の当たりにした時の驚きには影響しないだろう。近年の映画評で見かける「ネタバレ」とも無縁だ。まず、体調を整え、視覚と聴覚を研ぎ澄まし、スクリーンに向き合うだけでいい。
馬上鎗試合はこの作品のハイライト。映像もさることながら、交錯する音響の豊かさにも耳を澄ましてほしい 見逃してほしくないのが、『湖のランスロ』の森の黒さ。劇場だとその微妙なグラデーションの美しさが感じられるはず。そして、馬上鎗試合のシーンでの甲冑の金属音と馬の疾駆するリズミカルな音響に耳を澄ましてほしい。騎士たちが野営しているテントを行き来しながらコミュニケーションを図るシーンは、小津安二郎の『お早よう』(59)で新興住宅に住む婦人たちが互いの家を行き来するシーンのように見ていて飽きることがない。
環境問題、銃、ドラッグ、そして死への誘惑。若者たちが抱える不安を冷徹に見つめた『たぶん悪魔が』 『たぶん悪魔が』はラストシーンにとりわけ集中してほしい。夜の墓地の闇の深さ、簡素だが緊迫した台詞のやり取り、そして救いのなさ(フランスでは18歳未満の鑑賞が禁じられたこともあったという)。液晶の画面では十分ではない。フランソワ・トリュフォーが「すばらしく官能的」と称えた作品の魅力を上映設備の整った映画館でぜひ体感してほしい。1作2000円に満たない料金で、思わず息を飲む美しさに触れられると思えば、何とリーズナブルなことか。『マリ・クレール』フォロワーなら、そのことをわかってもらえるはず。必見!