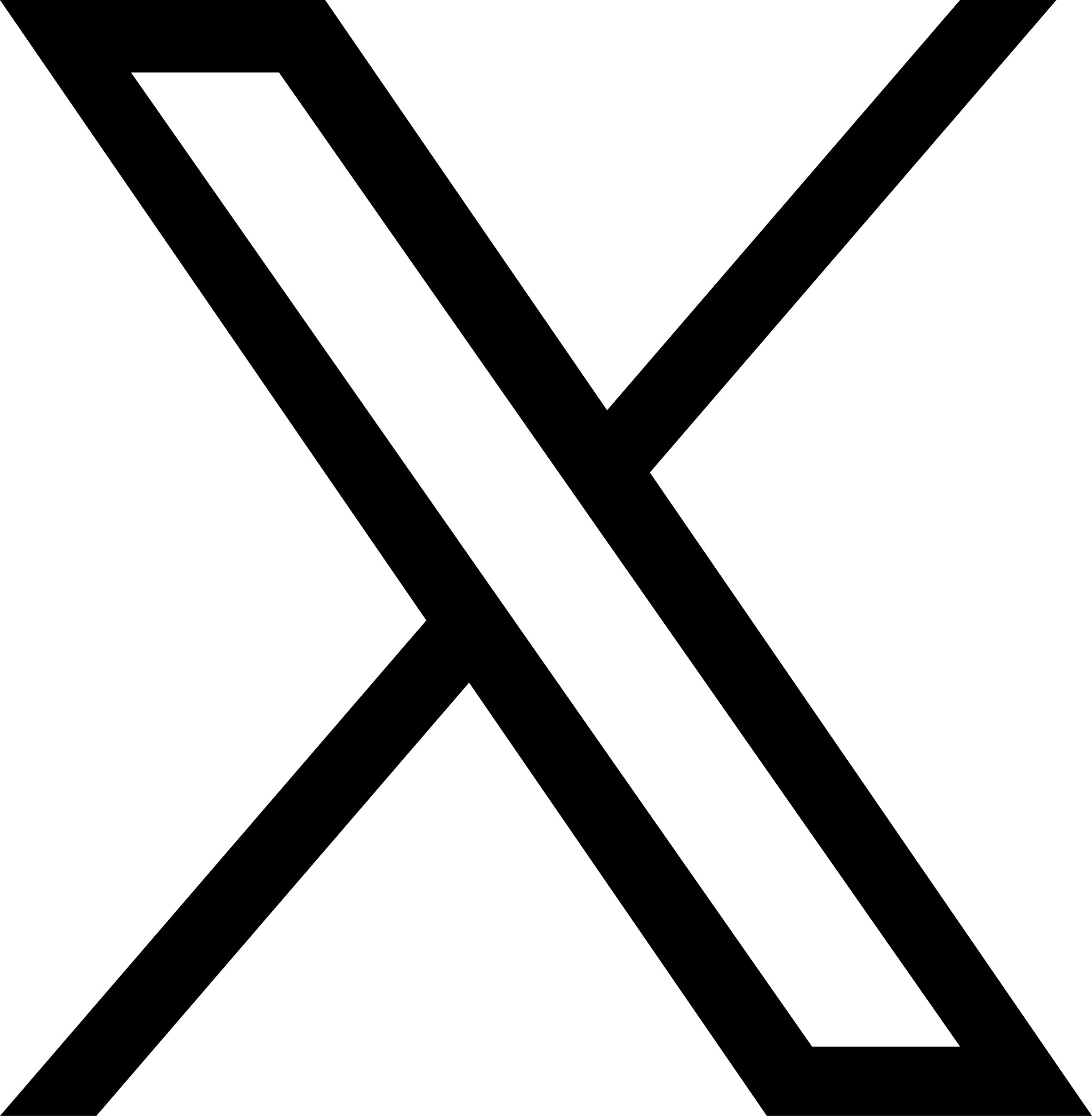【what to do】動体としての映画をいかにして文字に定着させるか。そのアクロバティックな試みを奇跡的に成し遂げた『日本映画作品大事典』を所有する喜びに浸る
ビジュアルを一切排除した事典の装丁は凄味すら感じさせる。それでも書影だけでは地味だと指摘され、映画関連の愛読書を並べてみた(撮影・高橋直彦)
知的好奇心に満ちた『マリ・クレール』フォロワーのためのインヴィテーション。それが”what to do”。今回は、2021年6月に刊行された『日本映画作品大事典』を紹介したい。「百年を超える日本映画史を一望のもとに見渡す、空前の作品データベース。」という出版社の惹句を裏切らない充実した内容。企画から発刊までに22年もの歳月をかけ、「映画」という融通無碍な表象を文字として定着させた。今年最大級の文化的達成を日本語の書籍として「所有」できる贅沢さを心の底から喜びたい。
映画は融通無碍で実は厄介な存在だ。作品を見ている時は面白がったり怖がったりしていればいい。ただ、作品を見終わって真面目に映画と付き合おうと思うと、掬い取った砂が掌から零れ落ちるようにスルリと身をかわしてしまう。ある種の出鱈目さを美点としてしまうところもある。近作でもその掴み所のなさに呆然とするのに、日本映画の歴史はすでに1世紀を超え、その蓄積も限りなく豊穣なのだ。それを遡行しながら、データベースとして定着させていく作業の難しさといったら……。
編者を務めた映画評論家の山根貞男さんも、出版元の三省堂の特設ホームページ(https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/jmovie/talk/ )の中で、封切日や作品の長さが参照する資料によって異なっていたり、作品タイトルが資料とフィルムで違っていたりしていて、「映画ほど事典に適さないものはないのではないかとさえ思うに至り、愕然とした」と心情を吐露している。
山根さんは映画批評誌『シネマ69』などの編集・発行を手がけ、『日本映画時評集成』を3巻にまとめ、映画祭で日本映画の魅力を海外へも積極的に発信してきた泰斗だ。それだけに、事典を「単なる作品リスト」にするのではなく、各作品に、どんな映画かが分かるような解説を可能な限り付けることを課した。消費された後は忘れられがちなプログラムピクチャーに力点を置いている点も「すべての映画は同時代的である」とする山根さんならではの編集方針だろう。
「小津安二郎」クラスになると、解説は7ページに渡る。執筆を担当したのは蓮實重彦さん。『世界大百科事典』(平凡社)でも「小津」の項目を担当しているのは同じ筆者で、読み比べてみても面白い(撮影・高橋直彦) さらに「映画の文献学」を志したものではないとも山根さんは宣言している。公開された映画をホルマリン漬けになった動物標本のようなものにはしたくないということだろう。動体としての「映画それ自体の輝きを文字として定着し、映画を愛するすべての人に届けるための基礎過程に過ぎない」とまえがきに記している。もっとも、動的な映画をスタティックな文字に変換することは、基本的に矛盾する「アクロバティック」な作業のはずだ。そのスリリングな作業の痕跡を追うことができるのも本書の大きな魅力の一つだろう。
編集部で見せてもらったゲラ。余白がビッシリと埋め尽くされるほど、修正点や疑問点が書き込まれ、目がくらむ。しかも、資料の束はほんの一部だという(撮影・高橋直彦) 事典の編集を手がけた瀧本多加志さんによると、22年の編集期間のうち、最初の5年が記載や収録のルール作り、次の5年が原稿依頼とその回収。そこから作品タイトルや公開年月日などの事実確認の校閲に10年がかかった。編纂期間中、一編集者だった瀧本さんは発行者でもある三省堂の代表取締役社長に就任した。企画から出版まで編集に関わった同社編集者の福島聖佳さんもプロジェクトがスタートして10年ほどが過ぎた時点で、膨大な作業量に心が折れかけ、「もし今やめたいと言われるなら、私は受け入れます」と山根さんに話したことがあるという。山根さん、編集者、そして執筆者の間でどれだけの遣り取り(駆け引き?)があったことか。そのプロセスをフレデリック・ワイズマンのような監督が記録してくれていたらと夢想する。
巻末には原稿の執筆者が48人挙げられ、担当した監督名が列挙されている。それに加えて短い項目などは編集部も執筆を担当した。執筆者がどんな監督を担当しているかをも比べるのも一興。「マキノ雅弘」を山根さんが担当しているのは当然としても、「黒澤明」を担当しているのは意外だった。そこでその項目を早速読んでみると……(撮影・高橋直彦) 黒い筒函に入ったB5判の真っ赤な布クロス貼の事典のブックデザインを手がけたのは鈴木一誌さん。映画批評も数多く発表している鈴木さんらしく、「顔で演技するな、怒鳴るな、等身大で喋れ」と演技指導をした澤井信一郎監督の演出術に自らのデザインが接近したと、山根さんたちとの鼎談の中で話している。それ故、組版はフラットになり、装丁もビジュアルな要素を排除したシンプルなデザインに。今風に言えば「映えない」装丁。しかし、「別にビジュアルにしなくても、読んでもらえれば分かる」という最終地点があったという。この潔い一言、澤井監督の師匠でもあったマキノ雅弘的とでも言うか、実に映画的なのだ。
「哀川翔」で始まり渡邊祐介監督の「刑事物語 くろしおの詩」で終わる事典の総ページ数は、巻末の索引なども含めて1072。重さは「鈍器」にもなりうる2078グラム。定価4万7300円だが、21年中に注文すれば、発売記念の特別定価で4万1800円。この価格、一見高価だが、実は割安なのだ。例えば、事典には約1300人の監督と約1万9500の作品が収録され、21年中の注文なら1監督あたり約32円。コンビニエンスストアで買うブラックサンダーほぼ1個分の価格にどれだけの知的な営みが込められていることだろう。 折しもクリスマスシーズン。親しい人に贈ってもいい。それほど親しくない人に贈っても功徳になる。もちろん、「頑張った自分へのご褒美」として買ってもいい。原則無観客で行われた東京五輪の熱狂も霞むほど、21年の出版界・映画界で最大級の成果と言ったら誇張し過ぎだろうか。日本映画史を網羅した世界でも希有な書物を日本語で手に入れられることの僥倖をしみじみと噛みしめたい。