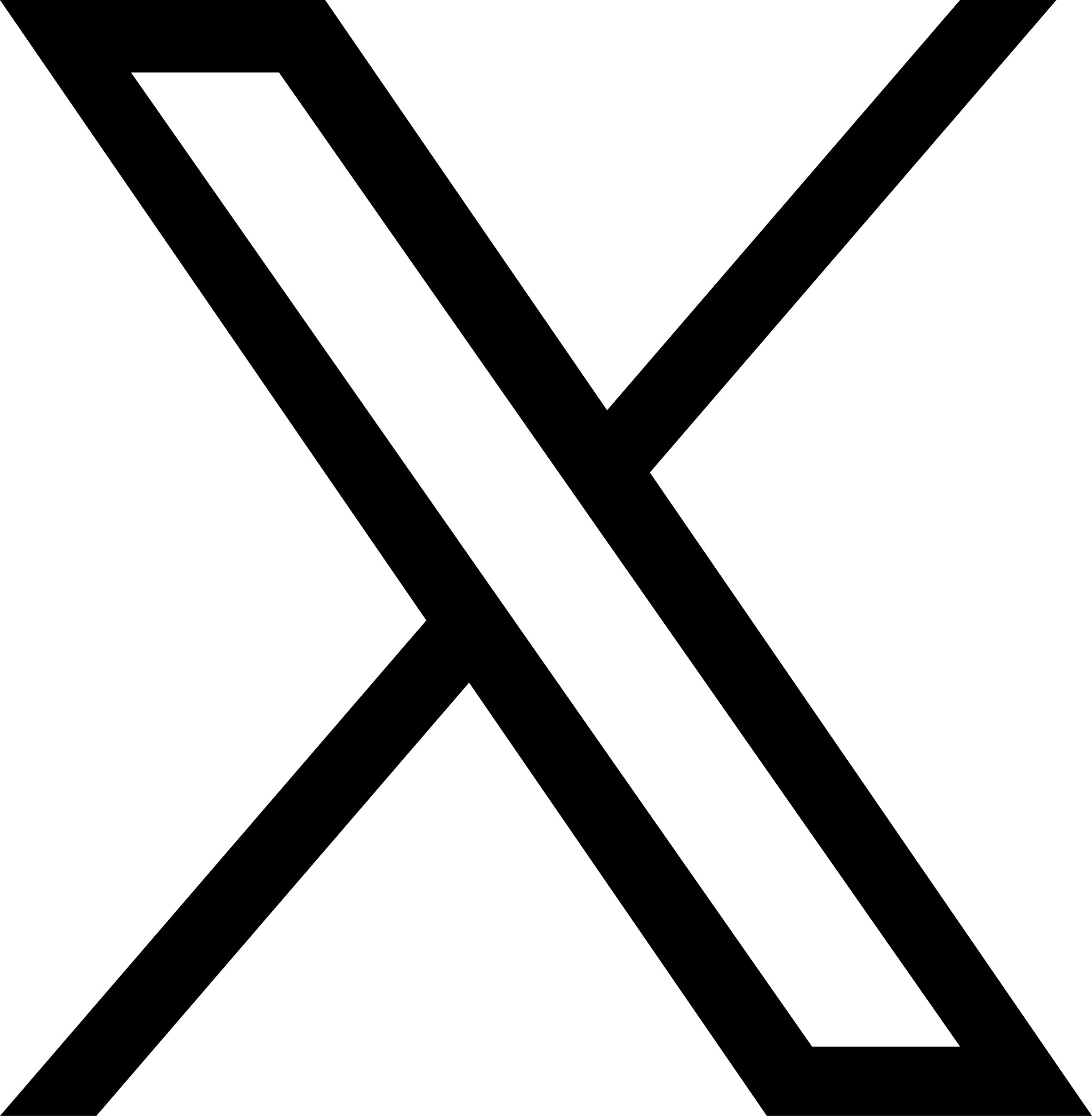【what to do】さわるとわかる、わかるとかわる! その豊かな連鎖にミュージアムで触発される
間島秀徳さんの作品「Kinesis No.743(dragon vein)」(2021年)に両手で触れて鑑賞する広瀬浩二郎さん(写真・国立民族学博物館提供)
“what to do”は知的好奇心にあふれる『マリ・クレール』フォロワーのためのインヴィテーション。今回、探求するのは「触れること」。パンデミックの影響もあって、この2年間、非接触のサービスやライフスタイルが広範に浸透した。その一方、「触れ合い」を欠くことで何か本質的なことを手放しかけてはいないだろうか? そんな危機感を共有する複数のミュージアムで、「触ること」をテーマにした企画展が開かれている。作品を「見る」、そして「聞く」。展示を通して、それら以外の感覚を拓き直す貴重な機会でもある。
11月初旬、愛知県美術館(名古屋市)で「曾我蕭白 奇想ここに極まれり」展を観た。伊藤若冲や長沢芦雪と並ぶ「奇想」のスーパースターだけあって、作品の多くが歪み、滲み、時に醜怪で観る人の感性を挑発しているよう。展示は11月21日で終わってしまったが、その醜怪さで印象に残ったのが「柳下鬼女図屏風」という作品。嫉妬のあまり鬼となった女の姿を描き、ガラス越しに近づいて一人で観ていると背筋がゾクゾクしてくる。当時も同じ思いをした人が多かったのか、顔の一部がはぎ取られている。
この二曲一隻の屏風絵、今でこそ温度や湿度管理の行き届いた展示ケースに入れられ、有り難い「美術作品」として鑑賞されているが、絵の描かれた江戸時代は鬼気迫る、もっと生々しい存在だったのではないか。そのことを、誰かが屏風に触れてはぎ取った鬼女の顔が象徴しているような気がした。
ユニバーサル・ミュージアム展のフライヤー表面には特殊な樹脂で点字がプリントされている。結構、お金がかかるらしい そんなことを思ったのは、名古屋展に先立って大阪の万博記念公園内にある国立民族学博物館でユニークな企画展を体験したからだ。特別展「ユニバーサル・ミュージアム ―さわる! “触”の大博覧会」(~11月30日)。タイトルに含まれる「ユニバーサル」という言葉を誤解してはならない。単に視覚に障害を抱える人や弱者支援に対応した社会福祉系の企画ではなく、コロナ禍の影響もあって広がった非接触文化について「触る」ことで再考を促す意欲的な内容なのだ。
企画を担当した同館准教授の広瀬浩二郎さんによると、今展は視覚偏重の近代化の過程で、人類が失ってしまった「感覚の多様性」を取り戻すための壮大な実験装置でもある。1967年生まれの広瀬さん自身、13歳の時に失明。筑波大附属盲学校から京大に進学し、同大学院で文学博士号を取得している。そんな広瀬さんの経験してきたことや思いも投影された「熱い」企画でもある。
興福寺仏頭の精巧なレプリカ。表面の微妙な凹凸まで再現され、触り応えがある(撮影・高橋直彦) まず、会場に入って驚かされる。国宝の興福寺仏頭が置いてあるのだ。とはいっても、白鳳期の金銅仏をFRP樹脂で忠実に再現したレプリカ。だから、自由に触れる。で、目を閉じて触ってみると、目で見た時のイメージと記憶が邪魔をして、手から得られる感触が形をなかなか結ばない。
それでもじっとあちこち触り続けていると、若々しい顔の表情がじんわりと浮かんできた。結構、肌に張りがある。仏頭正面に向かって右側に回り込むと、耳などが所々欠けていて、ギザギザした部分が仏頭の辿ってきた苦難の歴史を感じさせる。手のひら全体で触った時と、指先でなぞるように触れた時とでは受ける印象も違う。博物館などで正面から見上げているだけでは分からない、新鮮な体験だ。触って感じることに「開眼」した気分。面白い!
北川太郎さんの「時空ピラミッド」(2016年)の手触りはザラザラ。そっと優しく触るのが鑑賞のコツだ(写真・国立民族学博物館提供) 展示は導入部としての「試触コーナー」に加え、「彫刻を超克する」「アートで対話を拓く」「歴史にさわる」など6つのセクションに分かれ、計約280点の資料に触ることができる。例えば、「彫刻を超克する」のセクションに置かれている「時空ピラミッド」は石を使った彫刻を手がけている北川太郎さんの作品。薄くスライスした石材を人間の背丈ほど積み重ねた大作で、凸凹してザラザラした石の堆積に触れていると、制作にかかった時間の堆積も触知できそうな気がしてくる。
島田清徳さんの「境界 division-m-2021」は、全身を使って感じる作品(撮影・高橋直彦) 「アートで対話を拓く」セクションにある「境界 division-m-2021」も参加型で楽しい。島田清徳さんによる布片のインスタレーション。幅3.5メートル、長さ12メートル、高さ4.6メートルの空間に2000枚以上の白い布がつり下げられ、その中を自由に動き回ることで体にまとわりつく布の感触や衣擦れの音などを全身で感じることができる。
岡本高幸さんの「とろける身体-古墳をひっくり返す」(2021年)は墳墓の形状を全身でトレースする希有な体験(写真・国立民族学博物館提供) 「歴史にさわる」のセクションでは、岡本高幸さんの「とろける身体-古墳をひっくり返す」が印象深い。ポリエステル樹脂で巨大な古墳のデータを基に立体化し、それをひっくり返し、その窪みに人が入って古墳の形をトレースする。古代の墳墓に包み込まれる経験などそうあるものではない。頭で考える前に、体で感じることの面白さを文字通り体感することができる。
冨長敦也さんの《地平の人》(2004年)がフライヤーに印刷されたヴァンジ彫刻庭園美術館の企画展 みんぱく展に合わせるように、作品に触れられる企画展が開かれている。ヴァンジ彫刻庭園美術館(静岡県長泉町)で開催中の「すべての ひとに 石が ひつよう 目と、手でふれる世界」展(~2022年3月29日)もその一つ。みんぱく展にも出展している冨長敦也さんや北川太郎さんら、国内外のアーティスト計8人の石彫作品を展示している。
ホセイン・ゴルバ《自然を洞察し、瞑想するための7つの休憩場所、第5ストップ「水の音を聴く」》(2001年、参考作品) 同館では2020年から、より多くの人に開かれた「ふれる鑑賞」を推進していて、今展でも作品に手で触れて鑑賞する「触察」を勧めている。手に収まるサイズの作品も多く、多種多様なフォルムや素材を見るだけでなく、触れることで作家が石に込めた思いを感じ取ることができるだろう。今後予定されている作家によるワークショップも面白そうだ。いずれの施設でも、館内の換気を強化し、各所にアルコール消毒液を置いて手指の消毒を徹底している。念のため、言い添えておく。
真鶴町は「小松石」の産地として知られ、その石材を使った彫刻作品も展示されている ヴァンジ展に出展している作家6人を含む11人が参加して、神奈川県真鶴町で開かれているのが「真鶴町 石の彫刻祭 2021〉〉」(~11月30日、ただし、作品は恒久展示され、彫刻祭終了後も鑑賞できる)。こちらも野外彫刻展なので、基本的に作品に触れて楽しめる。ヴァンジ展の会場からもそう遠くなく、1日で両展をはしごできそうだ。
こうした展示を通して、日々の暮らしがいかに視覚に依存しているかを思い知らされた。しかも、スマホなどデジタルデバイスの普及によって、その依存度は年々高まるばかり。さらにコロナウイルスの感染拡大以後はソーシャル・ディスタンシングが強調され、「触れること」を忌避するライフスタイルも浸透した。上記の企画展は、そうした風潮に対して声高にではなく、あくまでやんわりと、しかし美術展らしい洗練されたスタイルで違和感を表明している。その思いに身体を駆使して感じ入っててみよう。見たり、聞いたりすること以外の感覚が拓かれていくことの快楽を体感できるはずだ。