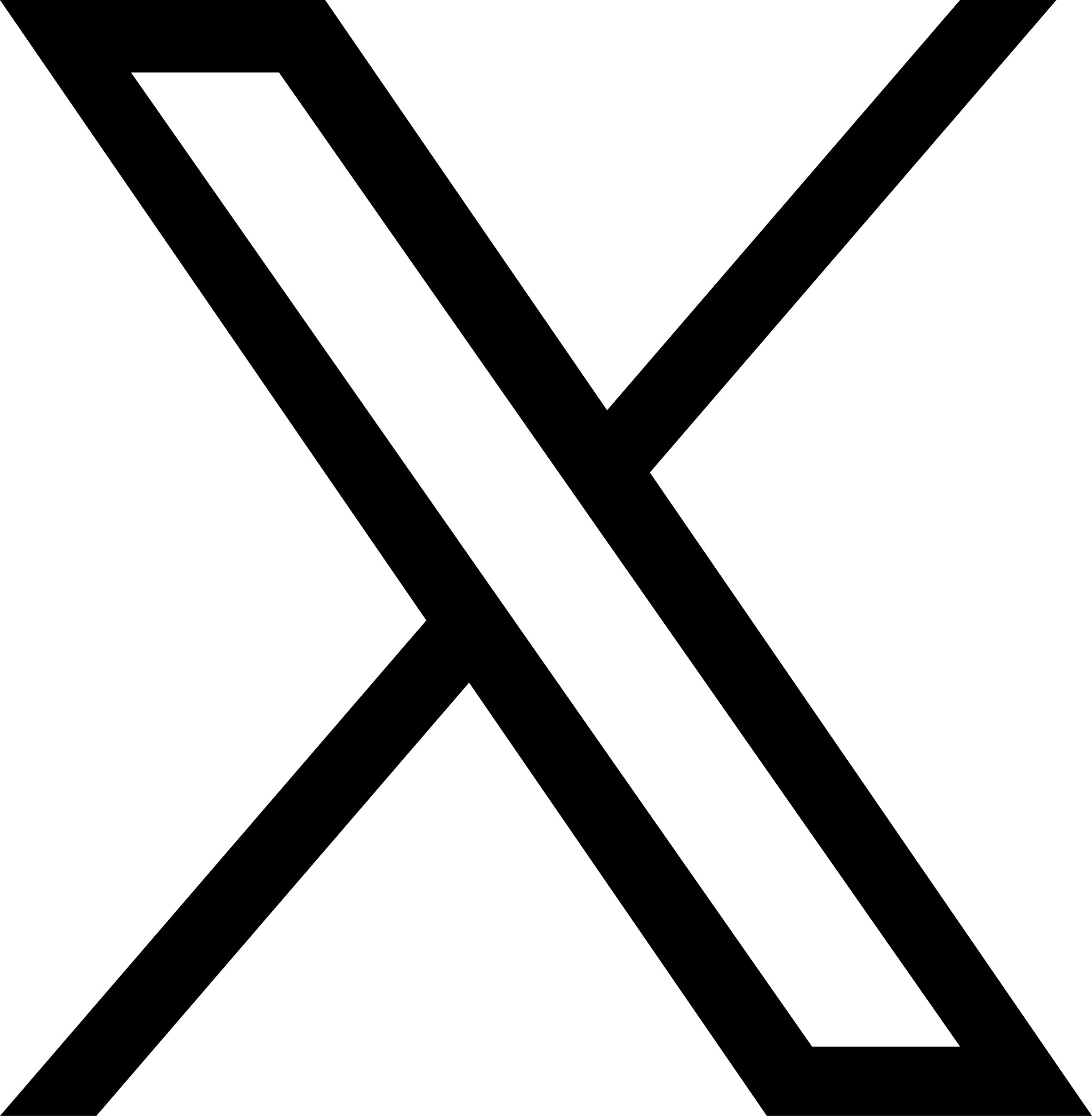【what to do】松濤美術館で開催中の「白井晟一 入門」展。美術館で美術館を鑑賞する愉しさを発見する
赤みを帯びた花崗岩が印象的な松濤美術館。ファサードが緩やかに湾曲しているのは、住宅地にある狭い敷地を少しでも広く見せるための工夫だったとか。よく見ると庇の下のライトがランダムに配置されている(撮影・高橋直彦)
知的好奇心あふれる『マリ・クレール』フォロワーのためのインヴィテーション。それが”what to do”。今回は、美術館で頻繁に開かれるようになった建築展について。実は見せ方が難しい。設計図や小さな模型の展示だけでは一般の人にとっては敷居が高いからだ。そこでどうしたか。空間を体感することのできる実物大の模型を造って展示の目玉にするように。一歩進めて、美術館の建物そのものを作品として見せる展示も。1月30日まで東京の渋谷区立松濤美術館で開かれている「白井晟一 入門」展もその一つ。白井(1905-83)晩年の傑作を素の状態で探索できるユニークな企画だ。
2020年夏、東京・砧公園内の世田谷美術館でユニークな企画展が開かれた。題して「作品のない展示室」。パンデミックの影響で、海外からの作品借用が難しくなり、展覧会準備に支障が出る中、逆境を逆手に取った。内井昭蔵(1933-2002)が設計して1986年に開館した美術館そのものを体感してもらおうという企画。一種の建築展であり、「美術館とは何なのか」、その目的や機能を見つめ直そうという意図もあったようだ。
(上)市民の憩いの場になっている砧公園内にある世田谷美術館(下)展示室の窓の覆いを取り外すと、公園の自然が借景に(撮影・高橋直彦) 内井は、広さ約38万平方メートルの広大な公園の自然と美術館を一体化させようと、建物に窓を多く設けた。もっとも、展覧会開催時は作品保護や鑑賞を妨げないよう遮蔽されていることが多い。その窓が開放され、照度や明度が管理された美術館とは異なる素の「明るい」表情を発見して驚いた記憶がある。それこそ、内井の提唱した「健康な建築」の現前でもあった。
展示作品を観覧するために訪れる美術館に「何もない」という異化効果もあった。作品を観ることに集中していると、展示空間を意識する機会は少ないが、その時は空間を体感することができるのだ。窓から差し込む外光の推移や空調のかすかな流れ、そして観覧者の気配も敏感に感じられた。逆に美術館でいかに頭しか使っていなかったかを思い知らされた。同館の関係者と雑談をしていると、意外に好評だったようで、美術館に普段足を運ばない人も結構、面白がってくれたという。
近年の建築展でも、空間そのものを体感できる「リア充」重視の企画が目立つようになった。設計図や縮尺模型だけでなく、実物大の模型を会場に設け、その中を観覧者が自由に歩き回れる「展示」手法もその一つ。例えば、森美術館(東京・六本木)で2007年に開催された「ル・コルビュジエ展」では、マルセイユ・ユニテのメゾネットタイプ(2階建てアパートの内部)と彼の終の棲家となったカップ・マルタンの休暇小屋の空間が再現されていた。17年に国立新美術館(東京・六本木)で開かれた「安藤忠雄展」では、野外展示場に大阪にある「光の教会」を忠実に再現して話題となった。さらに、21年秋、京都市京セラ美術館で開かれた「モダン建築の京都」展のように、美術館で紹介した建築を実際に巡ることのできるガイドをスマホ用アプリとして提供するケースも出てきた。
国立新美術館の野外展示場に素材も含めて忠実に再現された光の教会。その空間の豊かさを都心で体感できる贅沢さといったら。設置に約7000万円の費用がかかったとか(撮影・高橋直彦) 「モダン建築の京都」展は、美術館が近代建築を紹介するハブとなり、そこから街へ出て実作を見て巡る新しい鑑賞スタイルを提案した(撮影・高橋直彦) そこで今回の白井晟一の業績を振り返る企画展である。企画は2部構成になっていて、第1部が「白井晟一クロニクル」と題して、その業績を図面や模型などで辿るオーソドックスな回顧展(21年12月12日で終了)。書や書籍の装丁(中公文庫の表紙に描かれた鳥のイラストや新書の『RC』のロゴもデザイン!)なども含め、白井の創作を多面的に紹介してあり、見応えがあった。京都で図案を学び、哲学研究のためドイツに留学してカール・ヤスパースに師事するなど、ミステリアスな白井の人物像も企画担当者の丹念な調査によって浮き彫りにした。コンセプチュアルな建築を手がけた白井と、合理性を追求した住宅建築「SH」シリーズを発表した広瀬鎌二との接点について触れた展示が、個人的には興味深かった。
現在開かれているのが「Back to 1981 建物公開」と題した第2部。白井が「全力をだし切ったはじめての作品」とインタビューに答えている松濤美術館の建物を1981年の開館当初の状態で見せるという企画。世田美の「作品のない展示室」方式だが、今展で紹介している白井晩年の代表作を実際に体感できる場として企画されている点がユニークだ。
長年、渋谷区民だったこともあって、松濤美術館には足繁く通った方だと思うが、今回の展示で様々な発見があった。例えば、緩く湾曲したファサードの右手に、ブロンズの蛇口があることを初めて知った。「PVRO DE FONTE(清らかな泉)」とラテン語で刻まれ、会期中の金、土、日曜日は実際に水も流されている。白井の手がけた前橋市の書店に設けられていたものと同じだが、当初の計画にはなかったものだという。
ファサード右手にひっそりと設けられた蛇口。当初の計画にはなく、なぜ設置されたのか、その理由は今も謎だ(撮影・高橋直彦) エントランスの天井は薄くスライスしたオニキスをガラスに挟んだもの。その裏側からLEDで照らす。ゴージャス!(撮影・高橋直彦) エントランスから吹き抜けに掛かるブリッジを渡って地下1階の展示室へ向かうことができるのも今展の目玉だろう。通常、ブリッジの先は閉ざされているが、会期中はその先へ進める。当初、ブリッジの先に地下の展示室に降りる階段が設けられる予定だったが、導線の問題から途中で計画が変更された。4層の建物を貫く楕円形の吹き抜けは建物のハイライトで、底に噴水のある泉があり、それを見下ろし、あるいは空を見上げながらブリッジを渡って展示室に吸い込まれていくことは心躍る体験だっただろう。現在、展示室に降りる階段はないものの、白井のイメージした導線を追体験できる。展示室噴水側の窓も日光が直射するため、作品保護の観点から通常は遮蔽されているが、今回はその覆いを取り外し、竣工当時の明るさを取り戻している。
建物内部が楕円のシリンダー状になった松濤美術館。何とも豊かな空間で、来館者を非日常に誘う(撮影・高橋直彦) さらに地下2階にある茶室も初公開された。水屋を備え、炉も切ってある本格的な茶室だが、開館以来、茶室として使われたことはないという。何ともったいない! 美術館内にあるため、火の取り扱いなどで利用できないのだろうか。個人的に茶道を嗜むので、機会があれば使わせてもらいたいのだが……。さらに、白井が選んだデ・セデ(スイス)の革製ソファなど、豪華な調度にも注目したい。ほかにも書きたいことは山ほどあるが、いわゆる「ネタバレ」になっても興ざめなので、ここらで展示紹介はやめておこう。美術や建築の知識などは忘れ、とりあえず松濤へ駆けつけて空間の豊かさを堪能してほしい。
茶室は水屋も備え、本格的。生前、白井はここでくつろぐことが多かったという(撮影・高橋直彦) ヴィスコンティの映画に出てきそうな妖艶な雰囲気の館長室。担当学芸員による館内ツアーで見学できたが、まん延防止等重点措置で中止に。現在、実物を見ることはできないので、せめて写真だけでも……(撮影・上野則宏) 第2展示室のソファも竣工時の配置を再現。写真奥に見えるカウンターで注文したコーヒーを、かつてはここに座って飲むことができた(撮影・高橋直彦) 螺旋階段の細部のデザインや照明にも白井の美意識が宿っている(撮影・高橋直彦) 松濤美術館は本当に変わった建物だ。美術館なのに平らな壁面がほとんどなく、展示担当者の創意が試されるデザイン。さらに少し前まで、併設の厨房でコーヒーなどを注文して、それを飲みながら作品を鑑賞することもできた(会期中だけでも喫茶を再開してほしかったのだが、パンデミックがそれを……)。どうしてその意匠になったのか、説明が求められる近代建築にあって、謎に満ちた異色の存在なのだ。もっとも、時に効率性を超え、利用者側に立った仕様が多くの美術・建築ファンに愛されてきた。会期は残り少ないが、松濤美術館をじっくりと探索することで、美術館が単に美術品を格納して展示するだけの施設ではないことに気づくだろう。そして、美の洗礼を受けてきた『マリ・クレール』の読者なら、人間を包み込み、街並みを形成する建築をじっくり観ることの愉しさにも開眼するに違いない。