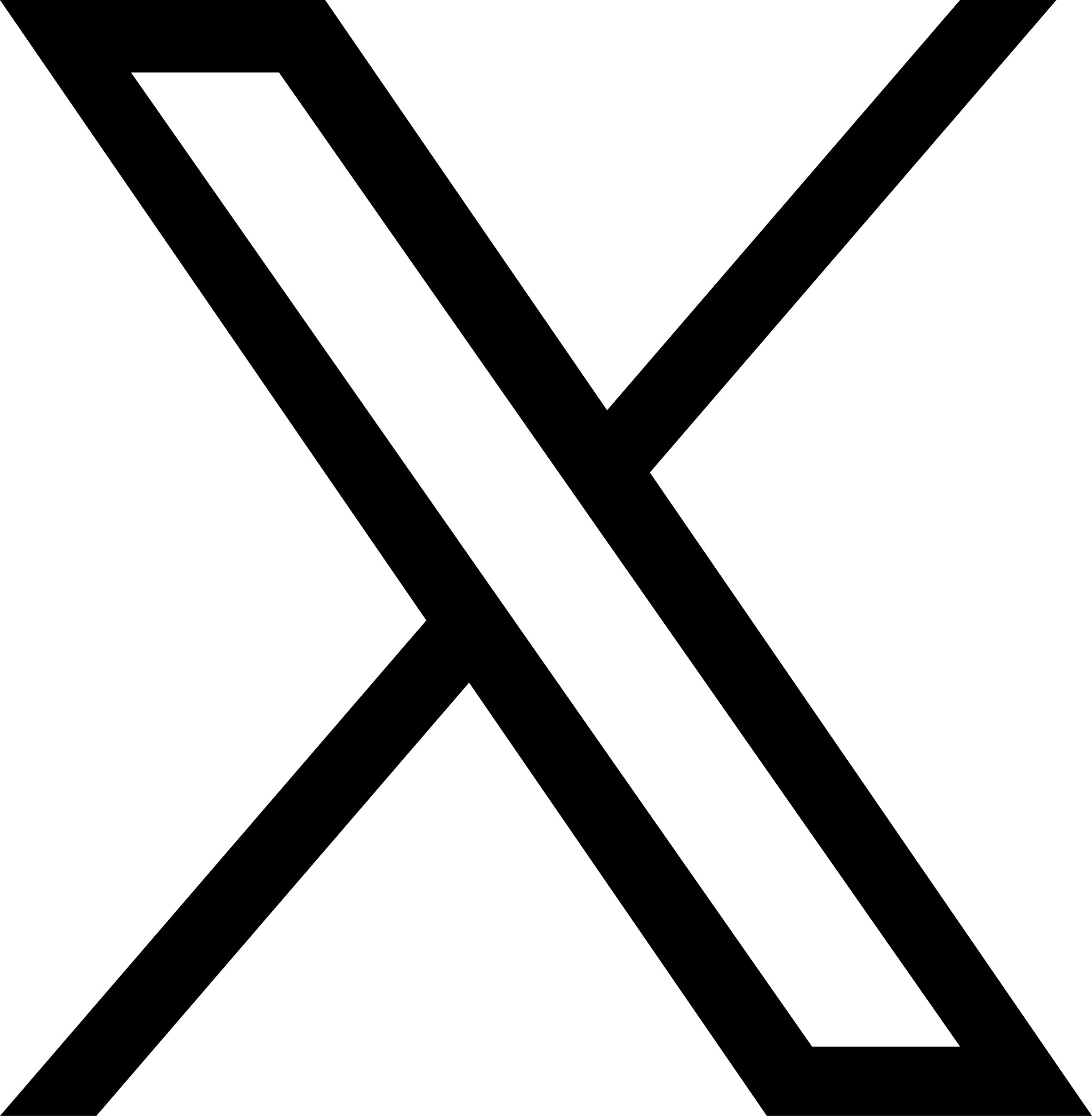【パリ発】故アルベール・エルバスにデムナ、川久保玲、アルマーニら46名のデザイナーが捧げた作品が一堂に
©Pierre Antoine
2021年4月、59歳の若さでこの世を去ったファッションデザイナー、アルベール・エルバス。21年10月のパリコレ最終日には、故人が生前に手がけた作品と、著名なデザイナー達が彼に捧げた46作品によるトリビュートショーが発表された。その全作品を集めた展覧会「LOVE BRINGS LOVE(愛が愛をもたらす)」が3月5日に開幕。7月10日までパリ・ガリレア美術館で開催されている。
アルベール・エルバスは1961年モロッコ生まれ。イスラエルでファッションを学び渡米し、ギ・ラロッシュやイヴ・サンローランを経て2001年にランバンのクリエイティブディレクターに抜擢される。そのデザインは多くの賞賛を呼んで老舗メゾンを復活へと導き、14年にわたってブランドをけん引した。21年1月には19年に立ち上げた自身の新ブランド「AZ FACTORY」の最初のコレクションを発表したが、それからまだ日も浅い4月21日に新型コロナウィルス感染症のため亡くなった。
故アルベール・エルバス氏 その温かい人柄で多くの人に愛されたエルバス。彼のデザインを象徴するフリルや大きなリボン、美しいテーラードやドレープ使いなど、46名のデザイナー達がそれぞれに解釈した46作品は、彼への愛と敬意に満ち溢れている。
©Pierre Antoine 作品と共にデザイナーから寄せられたメッセージをいくつかご紹介しよう。
バレンシアガ by デムナ
©Pierre Antoine 「彼のお気に入りのピンク色を用いて、バレンシアガ流ナイロンタフタのケープドレスを捧げます。彼のデザイン原則に従って、最小限の縫い目で最大のボリュームを表現しました」
クリスチャンディオール by Maria Grazia Chiuri
©Pierre Antoine 「最初に彼に会ったのはまだVALENTINOのクリエイティブディクターになったばかりの頃で、雑誌が主催したディナーでした。彼は慣れない私にすぐ声を掛け祝福してくれ、イベントの間ずっと一緒にいてくれたことを覚えています。彼の寛大さと共感は私に多くの感動を与えてくれました。その後彼は私の兄のような存在になり、彼の経験、知恵、愛は私をいつも啓発してくれました」
COMME DES GARCONS by Rei KAWAKUBO
©Pierre Antoine 「人間の脳は常に調和と論理を求めています。調和が否定される時、論理がない時、不調和がある時、、、あなたの内に混乱と緊張を感じる強力な瞬間が生まれます。それが前向きな変化と進歩をもたらすことに繋がるのです」
ラルフローレン
©Pierre Antoine 「アルベールに会うたびに、私は彼の暖かさとパワフルに生きる喜びに感動していました。彼はいつも大きな声を出すよりもささやく方が好きだと言っていました。彼のデザインはその静けさの美を映し出すようでした。彼は真のクラフトマンで、誠実な生き方をした人でした」
ドリス・ヴァン・ノッテン
©Pierre Antoine 「あなたの生きる喜び、才能、素晴らしい職人的な感性は、あなたが制作してきた全ての服に存在しています。私たちがあなたに敬意を示すために、この制作は我々にとって大切なことでした」
ジョルジオ・アルマーニ・プリヴェ by Giorgio Armani
©Pierre Antoine 「私はいつもアルベールの気さくでアイロニックな人柄が好きで、彼が描く楽しいタッチとグラマラスなスタイルに惹かれてきました。彼はいつも自由を愛する人でした。我々が特別な才能を持った彼を忘れることはありません」
OFF-WHITE by ヴァージル・アブロー
「アルベールへのオマージュ」*この作品は2021年11月に亡くなったヴァージル・アブローの最後の作品の一つとなった。©Pierre Antoine その他、アライア、アレクサンダー・マックイーン、バルマン、ボッテガヴェネタ、バルマン、クロエ、フェンディ、グッチ、エルメス、ジャンポールゴルチエ、ジバンシー、ロエベ、ランバン、メゾン・マルジェラ、リックオーエンス、サカイ、サンローラン、トムブラウン、ヴァレンチノなどが参加した。
本企画はアルベールが立ち上げた「AZファクトリー」の協力のもと、ガリエラ美術館がそのトリビュートショーと同じ舞台美術、音楽、照明を再現して構成した。さまざまなデザイナー達がそれぞれの解釈で観せる彼へのオマージュ作品は、生前のアルベールの優しさ、ユーモア、そして仲間への愛情に満ち溢れていたことを表現しており、見終わった後、改めてファッション業界が偉大すぎるデザイナーを失ったことを思い知ることになる。
取材・文:須山佳子