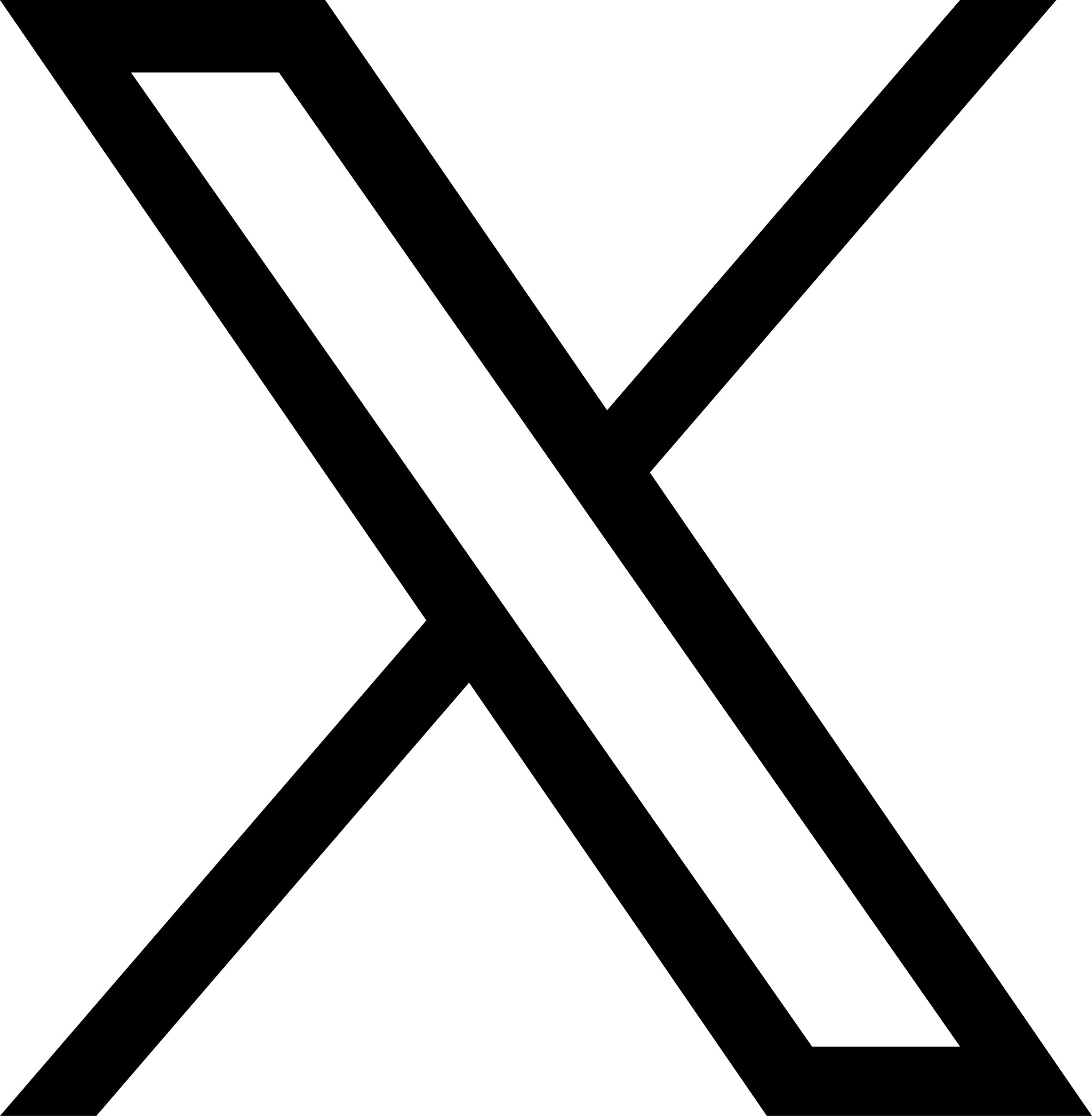<行定勲のシネマノート>第11回 ドキュメンタリーが面白い
(c)Nanmori Films
【9月13日 marie claire style】ドイツのフランクフルトで開催された「ニッポン・コネクション」という映画祭に審査員として招聘された。コンペティションにはフィクションとドキュメンタリーの日本映画が合わせて約20作品選出されていた。私たち審査員がニッポン・ヴィジョンズ審査員賞に選んだ『息の跡』と審査員特別賞に選んだ『愛と法』はいずれもドキュメンタリー映画だった。両作品共に新人の女性監督が手がけた作品で、とても魅力的な人間の生き方についての映画だった。
『息の跡』は東日本大震災後の岩手県陸前高田市で種苗店を営む佐藤さんという中年男性が生まれ育った町で未来を見据えながら、自らの津波の体験を英語や中国語で綴った本を自費出版し、自分の経験や得た想いを未来に残そうとする姿を描いた感動作だった。小森はるか監督が、大きな悲しみを抱え必死にもがきながら生きていこうとする被写体に出会って交流し、距離を縮めていくその関係性が反映されている素晴らしいコミュニケーション映画だと思った。
『愛と法』は、大阪に住むゲイカップルで共に弁護士のカズとフミの生活と仕事に密着し、LGBT、無戸籍者、逮捕されたアーティストなど彼らが弁護士として直面する社会問題と、行くあてのない少年を預かることで感情の変化が訪れ、やがて自分たちも子供を育てたいと思う個人の在り方を戸田ひかる監督が見事に描き出した。
2作品とも、被写体が可愛く魅力的。よくこんな人たちと出会えるよなぁとつくづく思った。それだけこの2人の監督は人間が好きなのだと思う。ドキュメンタリーは素材の力が大事だ。被写体の懐に飛び込み、信頼関係がいかに結べるかだ。その結びつきに至る前にまず出会いである。出会ってこの人を撮ってみたいという運命的な瞬間を逃したらここまで辿り着かないだろう。その人の味方になり、理解者になれるか。悪戦苦闘しながら答えのない道を辿る。その努力と粘りが映画に映っているところがドキュメンタリーの面白さだ。演出する側も被写体が悩み苦しむ姿に翻弄されながら、自分自身と向き合う。その葛藤が映画を深くする。人と出会うことは自分の人生を変えることだ。誰に出会ったかで人生は思いもしなかったところに向かうのだ。
出会いといえば、『愛と法』の戸田ひかる監督は、実は私の『世界の中心で、愛をさけぶ』のオーストラリアロケの撮影現場に初めてボランティアスタッフとして映画に参加した。彼女は当時メルボルンに留学していて、偶然にスタッフ募集のチラシを見て応募してきた。灼熱の太陽の下で働く我々ロケスタッフを、強烈な紫外線から守るために現場でひっきりなしに日焼け止めを塗って回っていたのが戸田ひかるだった。この出会いも彼女の人生を変えたのかもしれない。
あれから13年の月日が流れ、私たちは東京国際映画祭のパーティーで再会した。挨拶をしてもすぐに目の前の彼女があの赤い砂漠で走り回っていた女の子と直結しなかった。あのとき、映画になんて興味がなかった彼女が映画監督になって、しかも「日本映画スプラッシュ」部門で作品賞を受賞するような立派な映画を撮るなんて誰が想像するだろう。しかし、人生はわからないものだ。そんな予想もつかないものをありのままに撮るからドキュメンタリーは面白いのだ。
■プロフィール
行定勲(Isao Yukisada)
1968年生まれ、熊本県出身。映画監督。2000年『ひまわり』が、第5回釡山国際映画祭・国際批評家連盟賞を受賞。01年の『GO』で第25回日本アカデミー賞最優秀監督賞を始め数々の映画賞を総なめにし、一躍脚光を浴びる。04年『世界の中心で、愛をさけぶ』は興行収入85億円の大ヒットを記録し社会現象となった。以降、『北の零年』、『春の雪』、『クローズド・ノート』、『今度は愛妻家』、『パレード』(第60回ベルリン国際映画祭・国際批評家連盟賞受賞)、『円卓』、『真夜中の五分前』、『ピンクとグレー』などを製作。17年は震災後の熊本で撮影を敢行した『うつくしいひと サバ?』、島本理生原作の『ナラタージュ』が公開された。最新映画は、岡崎京子原作の『リバーズ・エッジ』。
■関連情報
・【無料ダウンロード】marie claire style PDFマガジンをチェック!
(c)marie claire style/selection, text: Isao Yukisada