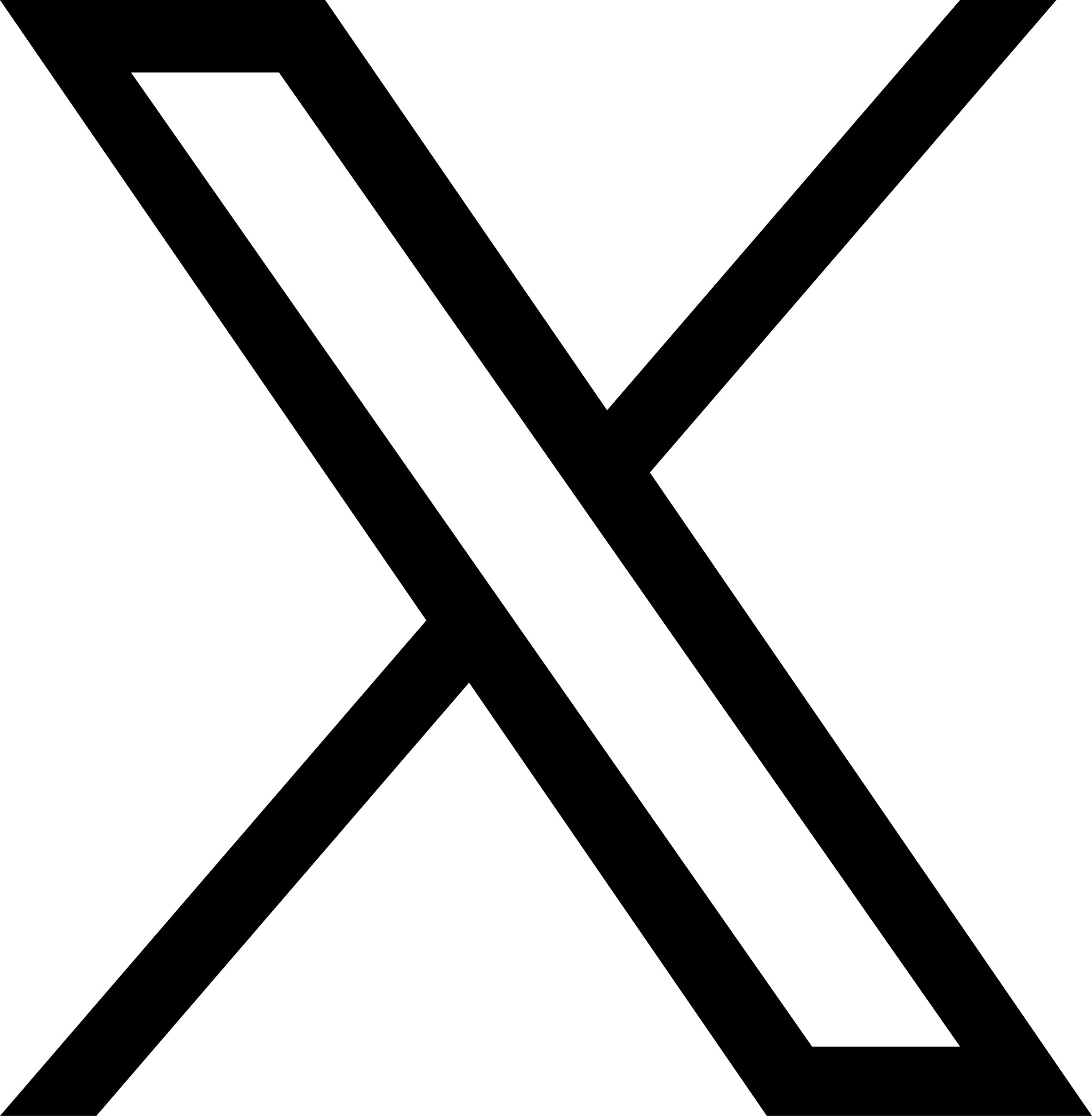【追悼・三宅一生】「ファッション」や「日本」という枠を軽々と超えてみせたデザイナーと同じ時代に居合わせた僥倖にまずは感謝したい
自宅の書架にあった一生さん関連の書籍・図録類。まだまだあるが、きりがないので途中でやめた(撮影・高橋直彦)
三宅一生さんが8月5日、84歳で亡くなった。20世紀末に新聞記者としてファッションの取材を始め、一生さんに国内外で話をうかがう機会があり、記事にしてきたこともあるだけに喪失感は計り知れない。それにしても多くの訃報が彼の肩書を「ファッションデザイナー」としているのは本当に正しいのだろうか? 「ファッション」という狭い枠組みに縛られず、「デザイナー」として幅広く活動した人こそ一生さんではなかったか。彼を失った空隙を埋め尽くせない今、取材者として創作の現場に立ち会えた僥倖に感謝することで、とりあえずの哀悼としたい。
ファッション取材を始めた1990年代半ば、パリコレに参加しているデザイナーの多くが東京でもショーを開いていた。一生さんもそう。単に服を見せるだけでなく、どう見せるか、その演出にも細心の注意を払い、新作の発表会というよりは、現代アートのカラフルなパフォーマンスを見ているかのよう。決定的に新しいことが、会場で生まれようとしている興奮と楽しさを体感した。82年に創刊した弊誌も及ばずながら、その活動に伴走してきたつもりだ。
「ファッション」と言っても、シーズンごとの微細な差異をあの手この手で提案する「トレンド」とやらに一生さんは大きな関心を抱いていなかったはずだ。その意味でも「ファッションデザイナー」という括りでは狭すぎる。むしろ、布と身体との関係性を「装い」を通して追究し続けたと言ってもいいだろう。それが和服から発想した「一枚の布」という彼の独創に結びつき、国内外で高く評価された。机上の空論で終わってしまいそうな発想を力技で実現に結びつけ、「プリーツプリーズ」や「A-POC」、そして「132 5. ISSEY MIYAKE」といったヒット商品を生み出した。
一生さんとの絡みでは、99年秋のパリでこんなことがあった。ある一般紙が「三宅一生引退」という記事を掲載。パリコレの取材中で、驚いてパリの事務所に話を聞きに行くと、真相はどうも違うようだ。その時に行われた春夏コレクションでデザイナーを交代したものの、創作は続けていくという。むしろ、やりたいことが山ほどあってうずうずしている様子。彼の気になっている若手アーティストがいて、その企画展を読売新聞と一緒にできないかとも話しかけられた。早速記事にして「『イッセイ』デザイナー交代」という見出しで、読売新聞東京本社発行の10月6日付朝刊社会面に掲載された。
その後の活動はご存じの通り。アーヴィング・ペン、イサム・ノグチ、エットーレ・ソットサス、倉俣史朗、ルーシー・リー、柳宗理、白洲正子、田中一光、インゴ・マウラー、市川房枝、荒木経惟、横尾忠則、安藤忠雄、蔡國強、森村泰昌、そして青森大学男子新体操部の部員たち……。協業や交流を重ねたのも、いわゆる「ファッション業界」以外の人たちが多かった。
2007年には東京に「21_21デザインサイト」を開設し、様々なデザイン関連の催しを企画。その時も朝刊の「顔」という人物紹介コラムで活動を紹介している。その中で「ファッション以外に、日本には優れたデザインがある」と発言しており、12年秋には当時、国立西洋美術館館長だった青柳正規さんらと、デザインを専門に扱う国立美術館設立に向けた活動も始めた。それも朝刊でいち早く報じることができた。その実現を今でも心の底から願っている。
恐らく、一生さんを失った悲しみや無念をこれから徐々に実感していくことになるだろう。しかし、自分にとっての一生さんは、二十数年前に「引退報道」が流れた時に見せた前向きな表情が原点になっている。そうした姿勢が様々な人たちにも散種されているはず。その結実を期待しながら、今は一生さんと同じ時代に生まれ、そのとてつもない創作に接することができたことへの感謝の想いを示しておきたいと思う。