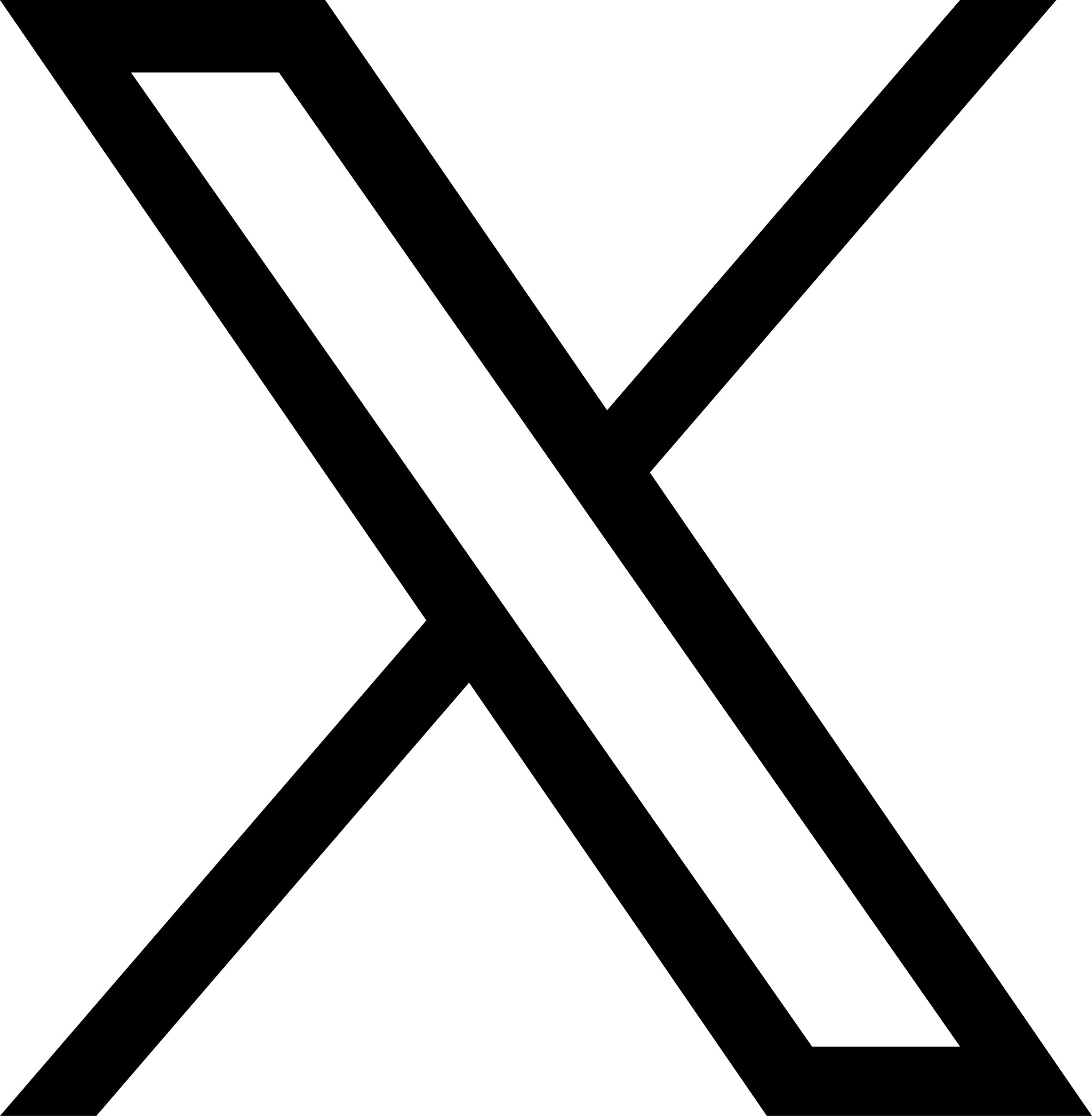【星のやを唎く】発酵文化の魅力を多彩な料理で表現。星のや東京でガストロノミーの最前線に触れる
非日常へいざなう。しかも、「圧倒的」な熱量で――。そうした思いを込めて星野リゾートが2005年から国内外で展開する宿泊施設「星のや」。そこで供される料理もゲストを日常から解き放つ重要な役割を担う。「美味しい」だけではない。「豪奢」なだけでもない。その場所、その季節、そして才能に恵まれた供し手たちがそろって初めて成り立つ料理というものがある。さあ、意識を研ぎ澄まして「星のや」を唎こう。初回は、日本各地に根付く発酵文化の魅力を多彩な料理で表現する「星のや東京」のダイニングから。
人がせわしなく行き交うビジネス街の大手町と、悠然と時を過ごす日本旅館ほど、縁遠いものはないだろう。その組み合わせの意外性に目を付けて2016年7月20日、「星のや東京」は開業した。すでに建物からして日本旅館としては破格だ。地下2階、地上17階の塔状の空間に、84室の客室を擁し、最上階の露天には温泉が湧く。その宿泊客だけに許される「特権」が地下1階にあるダイニングでの夕食だ。
【関連情報】〈宿泊券プレゼント〉星野リゾートの温泉旅館「界 加賀」の宿泊券を1組2名さまにプレゼント!
ダイニングのエントランス。その前に立った時から非日常の時間が始まる エントランスでは、地層をイメージした左官仕上げの壁と巨大な花崗岩のオブジェがゲストを迎える。すでに日常とは異なる時間が始まっていることを予感させる。客席は畳敷きの個室6席と、4つのテーブル席とカウンター。宿泊者限定とはいえ、前日までの予約が必須。そこで供されるのが、浜田統之(のりゆき)料理長の考案した「Nippon キュイジーヌ」だ。ほかのコースはない。「日本」はアルファベットで、フランス語で「料理」を意味する「キュイジーヌ」はカタカナでそれぞれ表記されている。一瞬、よくあるフュージョン料理を思い描いたが、そこは名だたる国際料理コンテストで入賞を重ねてきた気鋭の料理人。こちらの先入観など軽々と凌駕し、日本の食文化が凝縮された食材を、フレンチなどさまざまな技法を駆使しながら、驚きの一皿に仕上げていく。
ダイニングの個室は畳敷き。照明も抑えられ落ち着いた雰囲気で料理と向き合える 【関連情報】〈星野リゾート今だけバナシ〉絶景に乾杯!「ダイヤモンド富士」を湖上から鑑賞
2020年8月からは「発酵」をテーマにしたコースを季節ごとに提供している。2月28日までは、その冬メニュー。「ふぐ」や「ゆり根」、そして「ずわい蟹」など、冬場に旬を迎える食材を味わえる。しかし、なぜ「発酵」なのか? 広辞苑によれば、「酵母・細菌などの微生物が、有機化合物を分解してアルコール・有機酸・二酸化炭素などを生じる過程」が発酵だ。ミクロの世界で繰り広げられる作用によって醤油や味噌などの調味料や、漬物や塩辛などの保存食が作られてきた。滋味にあふれ、体にもいい。世界各地に発酵食品はあるが、湿潤な風土で微生物を食生活に取り入れてきた日本は発酵食品の宝庫でもあるという。「発酵という食文化を活かすことで食材の魅力をより引き出すことができ、星のや東京でしか味わえない料理をお出しすることができる」と浜田料理長は話す。
〈福〉ふぐの白子のパイ包み 食前に渡されたメニューには、供される料理を象徴する漢字一文字と食材などが記されるのみ。それゆえに料理への想像がかえって膨らむ。では、メニューの順番に沿って「福」から。「ふく」の発音から連想される「ふぐ」の白子のパイ包みがスターターだ。ふぐの卵巣の糠漬けと白子を、ソースペリグ-と共にパイ生地で包み、焼き上げた一皿。白子のねっとりとした食感とパイ生地のサクサクとした食感が口の中で渾然一体となる。ふぐの形をしたかわいらしい器にはふぐのコンソメが入っていて、ふぐヒレの入った猪口に入れてヒレ酒のように味わう。
それにしてもふぐの卵巣は有毒ではなかったか? それを手間のかかる発酵によって解毒するのだという。江戸時代から北陸を中心に伝わる技術で、卵巣を塩漬けにして水分を抜き、そこから塩抜きをして、糠味噌に漬けて発酵させる。時間も手間もかかるが、そうすることで、毒がゆっくりと抜けていく。それにしても日本人の食への執念の凄まじいこと。優しい味わいのパイ包みには、先人たちが試行錯誤を重ねた膨大な時間と食材への強い思いも凝縮されている。
料理に合わせて酒類のペアリングも楽しむことができる。このパイ包みには、シャンパーニュの「シャルル・エドシック ブリュット レゼルヴ」を合わせた。ピノ・ノワールの比率が多く、コクのある味わいがクリーミーな白子とマッチし、食欲を刺激する。
〈石〉五つの意思。左から【酸】鰊のルーロー(塩麹)、【塩】スープド・ポワソンとからすみ(カピ)、【苦】つぶ貝のコロッケ(醤油麹)、【辛】ホッケのブーダンブラン(辛麹)、【甘】鶏レバーペースト(豆酩) 続いて「石」。副題に「五つの意思」とある。ここでも語呂合わせが。料理長のスペシャリテらしい。五味(酸・塩・苦・辛・甘)をそれぞれ大理石の球形の器に載せた繊細な料理で表現した。味付けの全てに発酵食品を使っているという。例えば、「酸」を表現した鰊のルーローには塩麹を、「塩」を感じるスープド・ポワソンとからすみには、オキアミや海老などを塩漬けにして発酵させた「カピ」という東南アジア由来の調味料を使っている。
「苦」を味わうつぶ貝のコロッケには醤油麹を使い、「辛」のホッケのブーダンブランには唐辛子と柚を使った辛麹を混ぜ合わせている。最後、「甘」は小さなオペラのように見えるが、鶏レバーのペーストだという。これには豆腐を味噌もろみに150日以上漬け込んだ「豆酩(とうべい)」という発酵食品を使っている。いずれも指先ほどの小さな料理だが、しっかりと五味を感じられる。もっとも、その味わいが鋭い感じではなく、発酵食品の影響もあって、まろやかで複雑さも兼ね備えている。
これらの料理に合わせたのが、先のシャンパーニュにシェリーの「アルベアル アモンティリャード カルロスⅦ」を注ぎ足したもの。シャンパーニュに酸化熟成させたシェリーの風味が加わり、古酒を飲んでいるような錯覚に陥った。シャンパーニュにさらに複雑な表情が加わる。
〈時〉ゆり根のムニエル 次が「時」。収穫に約6年の歳月を要するとされるゆり根のムニエルだ。ゆり根の表面が黄金色になるまでバターを丁寧にかけて焼き上げ、フランス料理の伝統的なステーキソース、ベアルネーズソースを添えた。もっとも、そのソースに使っているのは「すんき」と呼ばれる長野に伝わる漬物で、乳酸由来の酸味がソースに瑞々しさを加える。
ゆり根のムニエルには、ドメーヌ・デュ・バヌレの「シャトーヌフ・デュ・パプ ブラン ル・サクレ 2017」を。ほっこりしたゆり根とスッキリした南ローヌを代表する白ワインが合う。
〈層〉ずわい蟹とリ・オレ 「層」は、冬場が旬となるずわい蟹のほぐし身を、コンソメのジュレとライスプディングのリ・オレに組み合わせた華やかな料理だ。リ・オレには日本酒を造る過程でできる酒粕を乳酸菌で発酵させた食品を使い、キリッとした酸味が蟹の旨味と絶妙にマッチする。
ずわい蟹とリ・オレの組み合わせには何を合わせるのだろう。興味津々に待ち構えていると、「ダッシュ ポーター・ヴァレー ドライ リースリング 2019」が出てきた。ドイツのモーゼルでもない。フランスのアルザスでもない。カリフォルニア・メンドシーノのリースリング。柑橘系の爽やかな味わいで、乳酸発酵酒粕の風味と心地よいハーモニーを奏でた。
〈和〉鴨と焼ねぎのすき鍋 そして「和」。鴨と焼ねぎのすき鍋が体を芯から温めてくれる。ローストした鴨の胸肉と焼ねぎの小鍋仕立てに何となく親しみがわく。割下に旨味成分の増した「熟成酒粕」を使って、まろやかな甘みを感じさせ、食材の深みを引き出している。
すき鍋には、ルールブック通り、ブルゴーニュの「マレシャル ヴォルネイ 2015」を。この地区らしい果実味あふれるスパイシーな味わいと、鴨肉に振りかけたマダガスカル産の野生胡椒「ヴィチペリフェリペッパー」の風味が絶妙に響き合う。
〈満〉苺とクレーム・シャンティ 最後は「満」。甘酸っぱい苺と生クリームを泡立てたクレーム・シャンティを合わせたデザート。クレーム・シャンティには、軽やかな酸味が特徴のレ・リボというフランス・ブルターニュ地方の発酵乳製品を使うことで甘さを抑え、上品な味わいに仕上げている。
このデザートに合わせたのは、仕込み水の代わりに酒を使った「山形政宗 貴醸酒 2016」。和三盆を思わせるかすかな甘みが、コースの最後を優雅に締めくくってくれた。考えてみれば、提供された酒類も発酵由来の飲料だ。食べ終えて、もたれる感じが全くない。発酵づくしのコースはきっと体にも優しいのだろう。
「Nippon キュイジーヌ」に適した食材を求めて国内外の産地を行脚する浜田料理長(中央)。取材した1月中旬も故郷の鳥取や岡山で素材を吟味してきたばかりとのこと 一皿一皿が創意に満ちた料理で、隙がない。それなのに食べ手を突き放さない優しさがある。ドイツ出身の建築家ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエが提唱した「Less is more」。その言葉を浜田料理長は大切にしているという。「限るから本質に近づく」という意味。それが自らの料理にも通じるという。「発酵」がその「本質に近づく」ための触媒になっている。ゲストと適度な距離を保つサービスにも「Less is more」の思いが通じている。
一応、ダイニングでの「食事」という体験なのだが、それを超えた未知の世界を、料理を通して識る喜びを感じた。日本文化の粋を世界に向けて発信しようという料理長やスタッフの意気込みも伝わってくる。それらが絶妙な化学反応を起こして、ゲストを非日常にいざなうのだろう。ちなみにミース・ファン・デル・ローエは、「God is in the detail(神は細部に宿る)」と言ったともされる。まさに「Nippon キュイジーヌ」のことではないか。「星のや東京」のダイニングで過ごす一夜は、この施設でこの時期にしか味わえない一期一会のアクティビティーでもあるようだ。